今日の諸悪の根源としてのダーウィニズム(4)
―人種差別の「科学的根拠」が最大の受容の契機―
優生学の問題として
一八五九年に出版されたダーウィンの『種の起源』は、なぜ欧米人による支持を次第に強めていったのだろうか。ダーウィン自身はむしろ恐る恐るこの仮説を提出したのであって、後世のダーウィニストが好んで言うように、進化論という自然法則を「発見」し「証明」したわけではない。この理論が、学説として大きな反対に遭いながらも確実に欧米社会に浸透していったことの背景には、それを強く要求する社会的事情があったと考えねばならない。
ダーウィンは自説の帰結として、無神論者とみなされることを怖れていたのだから、この説を支持する当時の欧米人にも、(現在のドーキンズのように)無神論の正しさが証明されたなどと言って喜んだ者は少なかったであろう。むしろそこは曖昧にしたままで、当時の欧米知識人に最も訴えたのは、この理論がそれまで曖昧だった人種問題に決着を与えたように見えたことであった。本来的に「劣った」人種というものがあるか、ないか、という問題は、特に十九世紀後半の解放奴隷を抱えるアメリカでは深刻な問題であった。ヨーロッパでは、この人種差別
の「科学的根拠」がヘッケルなどを経てヒトラーに渡り、人類史上最悪の人種抹殺という悲劇を引き起こしたことは、これまで論じた通
りだが、抹殺は論外としても、いかに「劣った」人種と共存していくかという別
の深刻な問題があった。
現在ではこれを論ずるのは、他人の容姿を論ずるのと同様、少なくとも表向きは、決して許されないことになっている。しかしこれまでにも述べたように、この時代の欧米知識人は、これを優生学という「科学」の問題として――よく言えば、世界を運営する責任者の問題として――おおっぴらに論じた。
このあたりについての文献をいくつか読んでみると、我々が想像する以上に、ダーウィニズム受容の契機が人種問題にあったことがわかる。その一つは、ジョン・S・ハラーの『進化から疎外された者――人種的劣等性という科学的態度、一八五九―一九〇〇』(John
S. Haller, Jr., Outcasts from Evolution: Scientific
Attitudes of Racial Inferiority 1859-1900, 1971)だが、この本から『種の起源』の出版前後に出版された本の挿絵を示しておく。
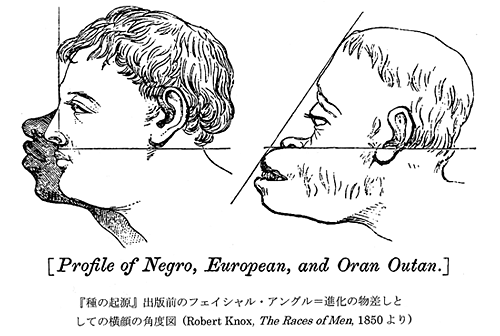
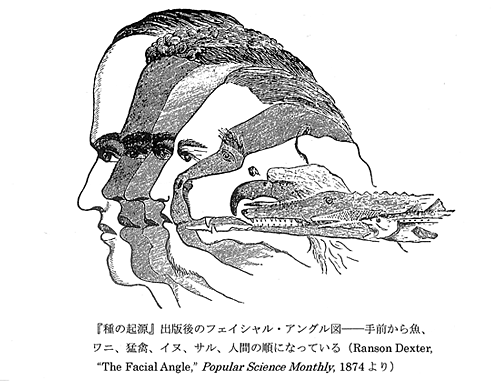
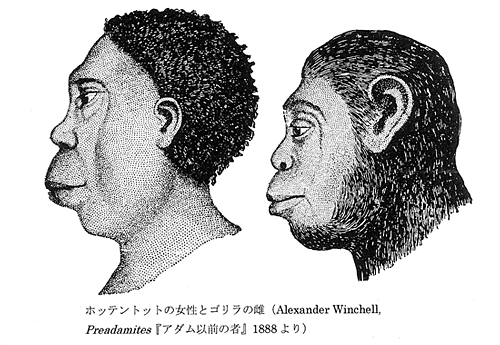
そもそも欧米人にとってダーウィン進化論の意味は、我々日本人の受け止め方とはかなり違うものであったことが、次のような記述に見て取れる。
人種的偏見という汚名を嫌がった多くの教育あるアメリカ人にとって、[進化論という]科学は、黒人種の本来的劣等性を「証明」し、参政権の剥奪と隔離という政策を社会科学の学術用語として合理化し、かつ中産階級の良心をなだめてくれるものであった。十九世紀の科学と社会科学の文脈において、人種的劣等という態度を理解することは、我々自身の時代の人種的偏見の深さを推し量
るための第一歩である。劣等性という観念が、彼らの進化論的思考枠の土台そのものであり、それがそのまま、科学的確かさという神話によって「真理」の頂上にまで高められた。この科学を装った人種的偏見に気付くならば、進化の概念と方法論が後に変化していったにもかかわらず、なぜ、人種的劣等という態度が西洋文化の障碍であり続けたかが理解できるだろう。(Haller)
ダーウィン進化論の欧米における「隠された生い立ち」ともいうべきものが、この文章でよくわかる。これが日本へは、後の「科学的確かさという神話によって真理の頂上にまで高められた」状態――いわばきれいな上澄みの状態――で入ってきたことを忘れてはなるまい。またこの文章によって、我々になかなか解けなかった謎、なぜダーウィン進化論が今日に至るまでこれだけしぶとく生き残り、かつこれを書いているまさに現在進行中の、ダーウィン陣営による理不尽なID弾圧が、なぜこれだけ堂々とまかり通
っているのか、という謎が解けてくるように思われる。
人種差別が内在する思想
しかし先走りする前に、これに関するいくつかの証言を引用しておきたい――
ダーウィン進化論は最初から人種差別
を内在させる思想であって、それは、異なったグループや人種が異なった時期と割合において進化してきた、だからあるグループは他のグループよりも、そのサルのような祖先により近いのだと教える。(Impact
Magazine, Aug. 2000)
人種間に大きな違いはないという事実、特に、ホモ・サピエンスと「より下等な」生物の主たる違いの最も重要な要因としての知力の差が、人種間にほとんどないという事実は、現在の進化理論の大きな難点となっている。その上、進化理論の悪用は、世紀の変わり目頃から長く続いて盛んだった、特に黒人とユダヤ人に対する極端な形での人種差別
の、重要な要因であった。(Jerry Bergman, 1993)
初期の進化論者の多くは、あけすけの人種差別
論者であった。そして人種的劣等という観点は証明済みのものと考えられていたので、今日我々が想像するほど議論や関心の対象にはならなかった。(同)
人種差別のための生物学的議論は、一八五九年以前にもよく見られたかもしれない。しかし進化理論の受容後、それは飛躍的に増大した。(Steven
J. Gould, 1977)
ダーウィンは『種の起源』では、人間の進化や人種についてはほとんど言及しなかった。彼が人間を論ずるようになったのは『人間の由来』(The
Descent of Man, 1871)においてである。現在のダーウィニストと同様、彼も最初はこの微妙な問題を避けた。しかしダーウィンもれっきとした人種差別
論者であったと、ハンバー(Paul G. Humber)は指摘している――「今日のダーウィニズム信奉者は、たいていの場合、人種差別
に関係付けられたくないと思っているので、この問題についてのダーウィンの発言が目に触れることが少ないのだが、ダーウィンは「ゴリラとニグロ」は進化上、「ヒヒと文明的人間(コーカサス人種)」の中間の位
置を占めていると言っているのだ。」
将来、何世紀というような遠い将来でないある時期に、文明を持つ人種はほとんど確実に、世界中の野蛮な人種を根絶し、入れ替わってしまうだろう。それと同時に類人猿もまちがいなく根絶されるだろう。そのとき、人間と人間に最も近い類縁のあいだの断絶はより大きく広がることになる。なぜならその断絶は、現在のニグロやオーストラリア人とゴリラの開きでなく、今よりもっと文明の進んだ人間――コーカサス人種をさえ超えた人種であろう――と、ヒヒのような下等なサルとの開きになるであろうから。(Darwin,
The Descent of Man)
背後に白人優越主義
一方、ダーウィンとその時代のイギリス人について、バーグマン(Jerry
Bergman)はこう言っている――
彼[ダーウィン]は奴隷制度は嫌っていたものの、彼の書くものはあらゆる種類の「原始的」種族に対する軽蔑に充ち満ちている。人種差別
は、モートンのカリパスによる頭蓋測定のような「科学的」トリックによって、教養あるヴィクトリア朝人の文化的に条件付けられた観念であった。
ダーウィン進化論は、欧米の白人種にとって真理であり科学でなければならなかった。このことを裏付ける事実は数限りなくあるようである。このように要請から生まれた教説をふつう「神話」という。一九二〇年代の『ブリタニカ百科事典』の「ニグロ」の項目には、黒人の持って生まれた知能的劣等性は、彼らの肉体的なそれより顕著なものだと書いてあるという。また一八八〇から一九八〇までに出版された科学の本では、白人は優秀であり黒人は「劣っている」と書くのが普通
であり、一九二〇年代には、教科書にまでそう書かれていたという。
サルと人間が通常の親子関係で――つまり「自然」の要因だけによって――連綿と続いているというのが、もし本当に「科学的事実」ならば、教科書には現在でもそう書かねばならないだろう。なぜやめたのか? なぜごまかすのか? とりわけ日本の場合は、指導要綱によってダーウィン進化論だけを教えるように言われているのだから、これについて生徒から質問があった場合には、「黄色人種である日本人は、黒人よりは優れていますが白人よりは劣っています」と答えなければなるまい。ダーウィニストは、サルに近いことは「劣る」ことではない、と科学の没価値論を持ち出すであろうが、これほどひどい詭弁はない。
もう一つ、ダーウィン進化論が「生物学的法則」でなければならなかった事例を引用しよう――
合衆国の一九二三年の移民に関する公聴会では、「生物学」は、ほとんどの東洋や南ヨーロッパの「人種」を排除すべきことを要求している、と多くの証人が証言した。異人種の流入を制限する主たる理由は、アメリカの血を純化し純粋に保つ必要性であった。その結果
として一九二四年四月、上下両院の圧倒的多数によって移民法が通
過した。カルヴィン・クーリッジ大統領はこの法律を支持しこう述べた――「アメリカはアメリカとして維持しなければならない。生物学的法則は…北欧白人種(Nordics)は、もし他の人種と混じり合ったら劣化することを示している」(Bergman)
米大統領選の行方にも
先日報道されたジェームズ・ワトソン発言(本年一月号参照)のように、黒人差別
の本音をポロリと洩らす者もいるが、普通はダーウィニストは、彼らの誇りでもあり恥部でもあるwhite
chauvinism(白人優越感情)を奥深く隠している。言論や学問の自由を擁護するはずのACLU(米国自由民権連合)という団体は、なぜ政教分離を口実にあくまでIDを押しつぶそうとするのか? 逆にダーウィニスト側が教室で宗教を利用しようとするときには、なぜ彼らは黙っているのか? 彼らの本当の動機は何か? ACLUは、一九七七年イリノイ州スコーキーで行われたネオ・ナチの示威運動を、正当な権利として擁護したことで知られている。
これを書いている現在、米大統領の予備選挙が進行中であるが、もしオバマ氏が大統領に選出されたときには、よからぬ
暴力的なことが起こる可能性が高いと思われる。そして手を下すのはダーウィニズム(ダーウィニストとは言わない)であること、そしてその真相糾明は結局うやむやに終わるだろうことも予測できる。IDをめぐるあまりにも理不尽なアメリカの動きは、このような予想を自然なものにする。
『世界思想』No.388(2008年4月号)
|人間原理の探求INDES|前の論文|次の論文|