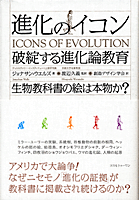 |
『進化のイコン』破綻する進化論教育
ジョナサン・ウェルズ著
渡辺久義監訳
創造デザイン学会訳
|
監訳者解説
本書はJonathan Wells, Icons of Evolution:
Science or Myth? Why much of what we teach about
evolution is wrong (Washington, DC: Regnery Publishing
INC., 2000)の全訳であるが、七十一頁に及ぶ巻末の詳細な「リサーチ・ノート」と、アメリカの生物学教科書を評価する付録等は割愛せざるをえなかった。ただ「リサーチ・ノート」については、著者の学問的厳密さと誠実さの証として本書の重要な部分であるので、著者にお願いして、ウェブサイトwww.iconsofevolution.comに掲載されることになった。特定の項目の関連文献や引用文の出典等について確認したいと思われる読者は、このサイト(または原著)を参照していただきたい。
誇張でなく、本書は衝撃の書だと言っていい。本書のきっかけとなったのは、「序」に書かれているように、若い生物学者としての著者の、生物学教科書に対するちょっとした不審であった。しかしその不審(あるいは不信)をやり過ごさず、徹底的に追及していくうちに、それは大きな驚きへと変わっていく。いったいどうしてこんな理不尽なことが生物学教育の世界で起こっていて、しかもそれが長年にわたって続いているのか、という生物学界全体に対する大きな驚きと疑念である。そして、この疑念はついに告発に変わっていくのである。
これは単に、生物学教科書の進化に関する記述に間違いが多いという話ではない。そうではなく、ほとんどの教科書が共通して昔から載せ続けている進化の証拠と称するものが、すべて偽物、ごまかし、ないし詐術に属するものだという衝撃的指摘である。
本書はその十項目を取り上げているが、それがすべてイコンの形を取っている。イコンとは、特にキリスト教東方教会で用いられる聖画像のことであるが、「進化のイコン」とは、進化論刷り込みの手段としての聖なる画像、というような意味である。現代なら、毛沢東や金日成父子の肖像がそれに当たるだろう。原著のエピグラフに引かれているスティーヴン・J・グールドの言葉にある「説得の画像表現法(イコノグラフィー)」というのがそれであって、生物学教科書はまさにこうしたいくつもの「聖画像」を伝統的に利用してきたのである。グールド(故人)はダーウィニストの総帥ともいうべき人物で、著者とは正反対の立場の人だから、この言葉を皮肉をこめて利用しているだけである。勘違いしてはならないので注意しておきたい。
これは我々のすべてが知っておかなければならないことである。なぜなら、我々が調べたかぎり(附記参照)、わが国の生物教科書についても事情はほとんど同じである。ダーウィニズム批判の本は少なくない。しかし少なくとも英語圏や日本の若者が、長年にわたって、ニセモノの証拠を使ったダーウィニズム洗脳教育を施されてきたという事実は、この本によって初めて明らかにされたと言ってよい。これは、必ず誰かが書かなければならなかった本である。
例えば、恐らく誰にでも鮮やかな記憶のある、あのヘッケルの胚の比較絵がそうである。これ(胚発生学)は著者の専門分野であり、この本のきっかけとなったものなので、ここは特に詳細に書かれているが、これを扱った5章の最後のセクション「これはひどい!」(Atrocious!)を読んでみていただきたい。まさか学問の世界で、教育の世界で、と思うようなことが現実に起こっている。スティーヴン・J・グールドはこの絵がニセモノであることを、とうの昔から知っていたという。そしてこれは「学問上の殺人に匹敵するものだ」と彼自身が言ったという。一方、恐らく最も有名なアメリカの教科書執筆者であるダグラス・フツイマはこれを知らず、自分の教科書に載せ続けていたという。グールドは、同じダーウィニスト仲間であるフツイマがそうしているのを、黙って見ていたことになる。だとすると、グールドはこの「学問上の殺人に匹敵する」大罪の共犯者になるのではないか、と著者ウエルズは言っている。誰しも「これはひどい!」と叫ばざるをえないだろう。
しかしフツイマが、単なるうっかり屋の素朴な生物学者でないことは確かである。それは、10章「ウマの化石と導かれた進化」の最後のところに引用されている彼の文章に明らかである。これはオックスフォード大学のリチャード・ドーキンズの文章ときわめてよく似ており、彼がヘッケルやドーキンズと同じ唯物論的進化論のイデオローグであることがよくわかる。恐ろしいのはこのイデオロギーが、中立的な科学的記述であるかのように、教科書に書き込まれることだとウエルズは言うのである。彼はこういった事態に対してどう防備したらいいのか、生物学者はどう行動すべきか、ということまで示唆している。特に最終章「進化論争の障碍」は教育にたずさわる人々に読んでほしい部分である。この本の結びの部分をどうしても引用したい。
……こういったことすべてが、いったいどうしてわかるのか? 証拠があるからか? 違う。それは、生物学は進化という観点から見なければ何ひとつ意味をなさない(と、ドブジャンスキーが言った)からである。
これは科学ではない。これは真理の探求ではない。これはドグマ(独断)である。そしてこういったものが科学の研究や教育を支配するようなことを、許してはならないのである。我々は、学生にダーウィン理論を植え付けるために進化のイコンを用いるのでなく、理論というものは証拠に照らして、いかに修正され得るものであるかを学生に教えるために、それを用いるべきである。科学の最も悪い面
を教えるのでなく、科学の最もよい面を教えるべきである。
進化のイコンを用いるなら、本当の科学者になろうと思うならこういうことをしてはいけませんよ、という「反面」教育の材料として、これを用いるべきだと著者は言っているのである。ダーウィニストには、これは腹の立つだけの皮肉に聞こえるかもしれない。しかし虚心にこの本を読みすすめてきた者には、これは著者の心の叫びに聞こえるだろう。
著者ジョナサン・ウエルズは、今アメリカを中心に急速に広がりつつある科学の新しいパラダイムである「インテリジェント・デザイン理論」(ID)の主導者の一人である。この本はID理論を解説するものではないが、ID派の特徴である、ダーウィニズム専制体制との対決姿勢を鮮明にもつものである。
IDとは何かについては、我々の運営する「創造デザイン学会」のホームページ(www.dcsociety.org)をご覧いただきたい。ここには「不適者生存」(原題Survival
of the Fakest・・最たるニセモノの生き残り)という、ウエルズ自身によるこの本の要約のような論文を載せているので、ご参考になるかと思う。もう一つ「オオシモフリエダシャク再考」というウエルズの厳密な論考も載せている。また、ウエルズとマッシモ・ピグリウッチというダーウィニストとのPBSテレビ討論も読めるので、参考にしていただきたい。
現在、原著の出版からすでに六年以上たっているので普通の本なら翻訳の対象にならないかもしれない。これまで遅れた理由には時が熟するのを待つという事情があった。しかしこの本はいわば現代の古典であって、遅まきながらわが国でも燃焼し始めるであろう議論の土台にならなければならないものである。時間の遅れにかかわらず翻訳されねばならないものであった。
ウエルズの原著は、二〇〇〇年に出版されるぎりぎりの時点までの学界の動静を、広く文献を渉猟しながら紹介しているから、その後どうなったか気になるところだが、「その内容と結論は今も変える必要がない」と彼は「日本語版への序」で言っている。これは最近(二〇〇六年)出たばかりのウエルズのPolitically
Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design
(Washington, DC: Regnery INC.)によっても確認できる。ダーウィニズムをめぐる論争(むしろ闘争)の様子はインターネットを通じても刻々入ってくるが、現在、ダーウィニズム専制体制は、明らかに末期症状を呈し始めたと言ってよい。これを物語るエピソードは数え切れないほどあるが、ここで紹介するわけにはいかない。ただ彼の仲間がもらしたという「これはまるでルイセンコ学説専制下のソ連そっくりだ」という述懐がすべてを物語るだろう。ダーウィニスト体制側が自分たちへの批判者に対して取る「物理的対抗措置」は、えげつないの一言に尽きる。
ウエルズの本の強みは、彼がすぐれた文章家であることと、その程よい諧謔精神である。本訳書を読んでもそれは伝わると思うが、新しい本ではもっと笑わせてくれる。要するにID派に余裕があり、ダーウィニスト側に全く余裕がないということである。
本書の翻訳は、「創造デザイン学会」の翻訳チーム六名が下訳をし、渡辺が全体を調整した。六名のうち五名までが理系の人たちで、医博二名、理博一名、工博一名、大学院農学研究科生一名、残り一名は若い気鋭の哲学者(文博)である。このうち何人かは、名前も所属も伏せてほしいということであった。この本の内容が内容であるだけに、(ウエルズ自身の「序」の最後にも書かれているような)経歴に危険が及ぶような可能性がないとも限らない。そこであえて全員の名を伏せることにした。監訳者としては、そういった事態がわが国で現実とならないことを願うのみである。
2006年11月 渡辺久義 |

