�������ȏ��Ƃ����ɕt���������i�P�j
-�w������M����i���_�L�q-
�i���_�Ƃ����̐�
�@�_�[�E�B�j�X�g�ł��蔽�h�c�i�C���e���W�F���g�E�f�U�C���j�h�̋}��N���[�W�F�j�[�E�X�R�b�g�iEugenie
Scott�j���j���A�_���Ō��܂����悤�Ɍ������t������B����́u�h�c�������Ɏ������肷��̂́A�w���ɑ���f�B�X�T�[�r�X�idisservice�j�ł���v�Ƃ������̂ł���B�f�B�X�T�[�r�X�Ƃ����̂́u�s�ׁv�Ƃ������ƂŁA���������i���_���炪�蒅���Ă���̂ɁA�����ᔻ����悤�Ȃ��Ƃ������Ċw���̓�������������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�Ȃ�قNJm���Ƀf�B�X�T�[�r�X��������Ȃ��B����������͂��傤�ǁA�j�����ڂ��Љ�̏펯�ɂȂ��Ă���Ƃ��ɁA�j�������v�z���q���ɋ�����̂��f�B�X�T�[�r�X�ɂȂ�悤�Ȃ��̂ł���B���Љ�I�ȁA�������Ȏv�z���w�Z�Ő������܂ꂽ�q���́A�Љ�ɏo�Ă�����A�����߂��A�s���v��ւ邾�낤�B����ł͎q�������킢�������B
�@�i���_����Ƃ������̂��A���Ȃ��Ƃ����܂ł̂Ƃ���A���傤�ǂ�����������ɂ������ƌ����Ă悢�B����͂܂��A����܂ʼn��x�������Ă����悤�ɁA���Y��`���́u�̐��v�Ɠ����ł���B�̐��ɏ]�����Ƃ��g�̈��S��ۏ��A�o���̏����Ƃ��Ȃ�B�̐��ւ̒����̂��߂Ȃ�A���X�̃E�\��c�Ȃ₱�����A�����̖����͂ނ���ϋɓI�ɋ��e�����B
�@����͉�������X�̐����̋��ȏ��Ɍ���Ă���B���m�̂悤�ɐ����̋��ȏ��ł́A�u���F�v�w���ł���i���_�ȊO�̊ϓ_����̋L�q�͋�����Ȃ��B���������Ă���͍̂��Z�p�u�������v�̋��ȏ��l��ނ��������A���s�̐������ȏ���ᔻ����r�c���F���w�V���������w�̋��ȏ��x�i�V�����Ɂj���Q�Ƃ��Ă��A����łقڑS�̂𐄂���
�邱�Ƃ��ł������ł���B
�����̋��ȏ��ł́u�i���v�Ƃ����͂�݂��āA���Ȃ�ڂ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���炵���̂����A���̋L�q���̂��猩���Ă�����̂�����B����͐i���_�Ƃ����u�̐��v�\�\�܂�v�z�����̐��\�\�ێ��̎p���̋������ƁA�����ɂ����ɕK�R�I�ɔ����]�тł���B
���M�҂����͖ܘ_�A�i���_�҂Ȃ̂ł��낤�B�������i���_�҂Ƃ����ǂ��A�i���Ƃ������Ƃɂ��Ċ��S�ɔ[�����Ă��āA������w���Ɋ�їE��Ő������Ă�낤�Ƃ������M�҂͂܂����Ȃ��ł��낤����A���̋L�q�͎��ꂪ�����A�����ȂׂĞB���ŁA�s�����ŁA�����͂̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă���B�{���̂Ƃ��뎩�M�͂Ȃ����A���ȏ��ɂ͂����������ƂɂȂ��Ă��邩�珑�����A�Ƃ����悤�Ȃ��̂������͂����͂��͂Ȃ��B��������ڂ��������w���ɂ͗e�ՂɌ����������ł��낤�B�����������̂�ǂ܂����قNj�ɂȂ��Ƃ͂Ȃ��B����ȏ�̊w���ɑ���u�f�B�X�T�[�r�X�v�͂Ȃ��B��������������Ă݂�B
�@
�J���u���A�����͖���
�@
�u���ݒn����Ɍ����鑽�l�Ȑ����͐i���̎Y���ł���B��܁Z�N�ȏ�̒������Ԃɂ킽�錤���̂����A�i���̏؋��₵���݂ɂ��ẮA�����̂��Ƃ��킩���Ă����B�v�i�������ЁA��Z�Z�܁j
�@�����Ɍ��炸�A���ȏ��Ŏg����u�i���v�Ƃ������t�͂��ׂĂ��̞B�����𗘗p���Ă���B�i����P�Ɂu���Ԃ������Ă̕ω��A���l���A���G���v�Ǝ��A�ŏ��̕��͂Ɉق�������҂͂��Ȃ��B�������i�����_�[�E�B���̂�����u�ω��������I���~�v�idescent
with modification�j�Ǝ��A���̕��͂ɋ^�O�����w�҂͂��Ȃ肢��͂��ł���B��̕��͂ɂ��ẮA�u��܁Z�N�̌����̌�ɂ��A�i���̏؋���d�g�݂ɂ��Ċm���Ȃ��Ƃ͂܂������������Ă��Ȃ��v�ƍl���Ă���w�҂̕����������낤�B�������i���_�u�̐��v�̂��Ƃł́A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�u�i���̒��Ԓi�K���������ΐ����̑��݂́A�i�����A���I�ɋN���������Ƃ��������̂ƍl������B�v�i���w�K�ЁA��Z�Z�܁j
�@ ����ȂǁA�����ɑ�_�s�G�Łu���F�v�̌Ղ̈Ђ���Ȃ���Ό����Ȃ����Ƃł���B������̃O���[�v���Ȃ��A���邢�͒��r���[�ȍ\�����������钆�ԉ��i�ڍs���j��������Ȃ����炱���A�i���_�����₦�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��B�u�A���I�Ɂv�ƌ����Ă��邩��A������Q���i���igradualism�j�R�����Ă��邱�ƂɂȂ邪�A�ł͂Ȃ��A�_�[�E�B�j�X�g�ł���G���h���b�W�iNiles
Eldridge�j��O�[���h�iStephen J. Gould�j�炪�u�f�╽�t���v�ipunctuated
equilibrium�j�Ȃǂ�������K�v���������̂��B
�u���������ʂ̑c�悩�炵�����Ɍ`��ς��A���܂��܂Ȓ��Ԃɕ�����Ă������Ƃ�i���Ƃ����B�v�i�[�ъفA��Z�Z�܁j
�@ ����͍Ō�́u�i���Ƃ����v�Ƃ����Ƃ�����u�_�[�E�B���i���Ƃ����v�Ƃ��Ȃ���A�������L�q�Ƃ͌����Ȃ����낤�B����͖��炩�Ƀ_�[�E�B���̂�����u�n�����v�ɒu�����L�q�ł��邪�A����ɋ^�₪�����������Ă��邱�Ƃ�S�������Ă��邩��ł���B�����w�҂̃W���i�T���E�E�G���Y�iJonathan
Wells�j�͎��̂悤�Ɍ����B
�@ �������ׂĂ̐���������́A���邢�͂킸���̋N���I�����̂́A�Q���I�ɕό`�����q���ł���Ƃ���Ȃ�A�����̗��j�͎}�����ꂷ����Ɏ��Ă��邱�ƂɂȂ낤�B�s�K�Ȃ��ƂɁA���̂悤�Ȍ��I�錾�ɂ�������炸�A���̗\���͂������̏d�v�ȓ_�ŊԈႢ�ł��邱�Ƃ����������B
���̋L�^�́A�����̎�v�Ȏ�ނ��A���ʂ̐�c����}�����ꂵ���̂łȂ��A�u�J���u���A�����v�ɂ����ĂقƂ�Ǔ����ɁA���S�Ȍ`���Ƃ��ďo���������Ƃ������Ă���B�_�[�E�B���͂����m���Ă��āA�ނ̗��_�ɑ���[���Ȕ��_�ɂȂ���̂ƍl�����B�������ނ́A����͉��L�^�̕s���S�̂����ŁA�����̌������܂��������Ă��Ȃ���c�������ƌ�����ł��낤�ƍl�����B
�������ꐢ�I���ɂ킽���đ�����ꂽ���̎��W�́A�����܂��܂��������邾���ł������B�킸���ȈႢ���ŏ��Ɍ���āA���ꂩ����傫�ȈႢ����Ɍ����̂ł͂Ȃ��āA��ԑ傫�ȈႢ���܂��ɏo���_�Ō����̂ł���B���Ό����҂̂���҂͂�����u�g�b�v�_�E���i���v�ƌĂ�ŁA�_�[�E�B�����̗\������u�{�g���A�b�v�v�̃p�^���Ƃ͖�������ƌ����Ă���B�ɂ�������炸�A�قƂ�ǂ̌��ݎg���Ă��鐶�����ȏ��́u�J���u���A�����v�̂��Ƃ��L�q���������A������A���ꂪ�_�[�E�B���i���_�^���˂�������̂ł��邱�Ƃ��w�E������͂��Ȃ��B
�@�u�J���u���A�����v�iCambrian
explosion�j�ɂ��ẮA�r�c���F�����w�E����悤�ɁA�킪���̋��ȏ����G��Ȃ����A�G��Ă����������ɍς܂��Ă���悤�ł���B���̗��R�͖��炩�ŁA�����Ɍ����Ă���悤�ɁA�_�[�E�B�j�Y���̐��ɂƂ��ēs������������ł��낤�B
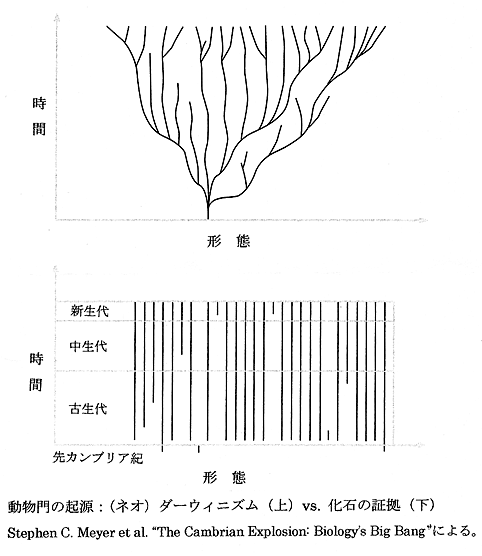
���ȏ��𗠓ǂ݂���
�@�ȏ�ɋ������悤�ȗ�́A�i���_����Ƃ������̂̍s���������u�d�����Ȃ����Ɓv��������Ȃ��B�������u�d�����Ȃ��v�ł͍ς܂���Ȃ��[���Ȗ�肪�������ȏ��ɂ͂���B
�@�����Ŏ��́u�����v������Ă��鍂�Z�����N�ɁA����s���Ă��������������Ƃ�����B���N�͂����炭�A�u�i���v�͖̏͂�
�������Ȃ������ɂ��o�Ȃ��̂Łi�H�j�A���N�ɓǂ܂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����łƂɂ����A��x�����������Ɠǂ�ł݂Ă������������B�����Ă��̏�ŁA��Ɉ��p�����W���i�T���E�E�G���Y�̕��͂̏o���ł���u�s�K�Ґ����v�Ƃ����G�b�Z�C�S�̂�ǂ�ł݂Ăق����B
�@�E�G���Y�͓�Z�Z�Z�N��Icons of Evolution �i�w�i���̐��摜�x�j�Ƃ����Ռ��I�Ȗ{���o���A�u�Ȋw�͍��A�_�[�E�B�����_�̒��ƂȂ��Ă�����̂̑������A���U���邢�͐l����点����̂ł��邱�Ƃ�m���Ă���B�����������̋��ȏ��́A���ς�炸�����i���̌����̏؋��Ƃ��Čf�ڂ��Â��Ă���B����͂����������ȏ��̗��Ȋ�́A�����Ӗ�������̂ł���̂��H�v�Ƃ����^����A�����w�E�Ƃ������Љ�S�̂ɓ˂������B�c�O�Ȃ��炱�̖{�͍��̂Ƃ���M�Ȃ��B�����ŁA���̖{�̗v��Ƃ�������u�s�K�Ґ����v�i�����Survival
of the Fakest�A�ł���j�Z���m�̐����c��j�Ƃ����l�b�g��ŊȒP�ɓǂ߂�G�b�Z�C������B����Ƃ�����A�������҂ɂ��u�I�I�V���t���G�_�V���N�čl�v�Ƃ����_�����ēǂ�ł݂Ă������������iwww.dcsociety.org�j�B��R�A��������
�����Ȃ�͂��ł���B
�@�����̘_���́A���ɂh�c��n���_�̗��ꂩ��ᔻ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�P���ɁA�u�����ׂ����Ƃ������̋��ȏ��ł͋N�����Ă���A���������ǂ��Ȃ��Ă���̂��v�Ƃ����f�p�ȋ������琶�܂ꂽ���̂ł���B
�@�܂��u�I�I�V���t���G�_�V���N�̍H�ƈÉ��v�Ƃ����L���B����͓`���I�ɂقƂ�ǂ̋��ȏ�����
�^����ōڂ��Ă���悤�ł��邪�A����͒r�c���̑O�L�̖{�ł������Ă���悤�ɁA�����A�L�ڂ𒆎~���ׂ����̂ł���B���̍����́A��L�E�G���Y�́u�I�I�V���t���G�_�V���N�čl�v�Ƃ��������ɘ_�����_����{�ŏ\�����Ǝ��͎v���B�ڂ����͂����ŏq�ׂȂ����A���F�ƈÐF�̃V���t���邪�̊��Ɏ~�܂��Ă����
�^���̂��̂��j�Z���m�ł���Ƃ����B�������Ӓn���Ȍ�����������A���ꂪ���ȏ����������O�ɂ������茩�Ă����Ă������������B�E�G���Y���͂��̘_�����u�w������M���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������͂Ō���ł���B����͒P�Ȃ��L�����ł͂Ȃ��B�Ȃ������������Ƃ��N�����Ă���̂����A�l���Ă݂Ă������������̂ł���B
�@���������Ƃ悭������́A�_�[�E�B���E�t�B���`�i�K���p�S�X�E�t�B���`�j�ɂ��ẮA������`���I�Ȓ�ԂƂȂ��Ă���L�ڂł���B����͝�鯂������Ɖa�̎������̂�����ɂȂ�̂ŁA���̏����̂������̕��ς̑傫�����킸���ɑ����A�J���߂�܂�����
�̃T�C�Y�ɖ߂�Ƃ������R�I���́u���́v���������A�����̒����Ɋ�Â����̂ł���B���̌����������͖̂�
�����Ƃ��Ă��A����Ȃ��Ƃ́A�V���t����̉H�������Ȃ����蔒���Ȃ����肷�錻�ۂƓ��l�A�����̐i���ɂ͉��̊W���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���i������u���i���v�ł����Ȃ����낤�j�B
�@�Ƃ��낪���ꂪ�A�i�s���̐i���̍D��Ƃ��ē`���I�ɋ��ȏ��ɗp�����A�E�G���Y�ɂ��A�����N�u�A�����J�����Ȋw�A�J�f�~�[�v�o�ł̃u�b�N���b�g�ɂ́A����͎�̋N���́u����
�ɐ����͂̂����v�ŁA�u�\�N�Ɉ��̊����ŝ�鯂��N����A�V�����t�B���`�̎킪��S�N���炢�Ő��܂��\��������v�Ə�����A�������J���߂�������̃T�C�Y�͌��ɖ߂�Ƃ��������͕����Ă���̂��Ƃ����B�N���l���Ă����炩�ɂ���͍��\�ł���B
�@���̌����l��ނ̋��ȏ��́A�������������L�ڂ��Ă��邪�A�������ɂ���ȍ��\�I�L�������͔����Ă���B����������͂��̃u�b�N���b�g�̂悤�Ɏ������B���Ă����i���̐����ɂȂ�̂ɁA�ϓ��̎����𐳒��ɐ}�Ő������Ă��鋳�ȏ��i�[�ъفj������B����͐����Ȃ̂͂悢���A�w���͐i���Ɖ��̊W������̂����b�Ɏv���ł��낤�B�������A�t�B���`�����ȏ��ɍڂ�悤�ɂȂ��������Ƃ̌o�܁i���@�A���_�j��m���Ă݂�A���_�������ƂƂ��ɁA���ȏ����M�҂̋�a��_�[�E�B�j�Y���̐��\�\�܂��X�̕����̑̐��\�\�Ƃ������̎���������ɂ킩���Ă��āA�w���̋����͂ɂ킩�Ɋ���������ł��낤�B���ꂪ�{���̈Ӗ��ł̊w���ւ́u�T�[�r�X�v�Ƃ������̂ł���B����I�ȁu�^���v�݂̂������A���Ή����Ă݂�藧�Ă��w������D�����ƁA������u�f�B�X�T�[�r�X�v�Ƃ����B
�@������A�u�����w��̍ł��L���ȋU���v�ƌ����Ȃ���A�w���͉���m�炳��邱�Ƃ��Ȃ��A���ׂĂ̐������ȏ������R�ƍڂ������Ă�����̂�����B����͂��̒N�ɂ��o���̂���w�b�P������̔�r�G�ł��邪�A����ɂ��Ắu�s�K�Ґ����v�̐}�Ɛ��������Ă����Ă������������B���ȏ����͂Ƃ��Ă����ꂭ�炢�ŏI���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�w���E�v�z�xNo.368�i2006�N6�����j
�b�l�Ԍ����̒T��I�m�c�d�r�b�O�̘_���b���̘_���b